こんにちは、クマノミです。
今回はコミュニケーション編という事で、「聴く」事に特化して、書いていきます。
実は、全人類共通した願望の中に、「話を聴いて欲しい」という事が大きくあります。
なぜなら、人は自分のことや自分の知っている事などを話したい生き物だからです。
本当に聴けている人って少なかったりするんですよね。
今回はこちらの本を参考に記事を書いていきます。
500Pと中々分厚い本でしたが、非常に示唆に富む内容でした。
僕たちが普段、何気なく会話している中でも、双方ではなく一方通行の会話になっている事も気づかされます。
「聴く」という事はどういうことなのか?
興味や関心を持つこと

これが本書の大雑把な結論になります。
ポイントは「興味関心を持つ」という点です。
このポイントに対して、様々な角度から言い方を変えて、重要性を訴求しています。
それくらい、僕たちが普段の会話で出来ていないという事ですね…
以前、コミュニケーションのブログでも書きましたが、相手に興味を持つことがコミュニケーションの入口であり、ベースとなります。
なので、聞き上手と言われている人は、例外なく話し手への興味を持って話を聴いています。
言い方を変えると、「好奇心旺盛」とも書かれています。
人に興味を持つという事は、「様々なことを知りたい」「あなたの事を知りたい!」と思う人です。
愛着理論

愛着理論…乳幼児が、不安や不快などストレスを感じている状況で、自分の親など周囲の養育者に対して泣いて訴える、あるいは接触を求めて甘えるなどして、親密なきずなを形成しようとする愛着行動に関する理論。 コトバンクより引用
イギリスの児童精神医学者であるジョン・ボウルビーが、1960年代に提唱した理論です。
「アタッチメント理論」とも言われているみたいですね。
要するに、ストレスを感じた際に親に対して泣いたり、触れることを求めて、親密な関係を築こうとする行為です。
本書では、その愛着理論を「聴く」視点で以下のように記載されています。
更にこう続けています。
一歳になるころまでには、赤ちゃんの脳には、親や養育者が如何に自分の欲求にこたえてくれたかに基づいて、人間関係はどういうものかの自分なりのテンプレが刻まれます。
概念の説明から入るとわかりやすいですね。
結局は、どれだけ小さいころに親や養育者が子どもの話を聴くことが出来るかが、その後の将来、その子の聴く姿勢に影響するという事です。
「聴く」事が難しい理由

誰もがみんな「話したがり」
あなたも経験あるのではないでしょうか。
自分の知っている事って、話し始めると気持ちいいですよね。
特に論理的に話せたり、笑いが取れたり、周りが「うんうん」と食いついてきたりしたら、もう最高!ってなりますよね。めちゃくちゃわかります!
他にも、お酒の席で上司や先輩がする自慢話が分かりやすいかもしれませんね。
お酒が入るので、自制心も低下しているので顕著に出ますよね。
そしてもう一つ、知っていることを話したいという事は、教えたいという事です。
これは、新入社員の皆さんにぜひ知っておいてほしいのですが、「先輩社員も例外なく教えたがり」です。
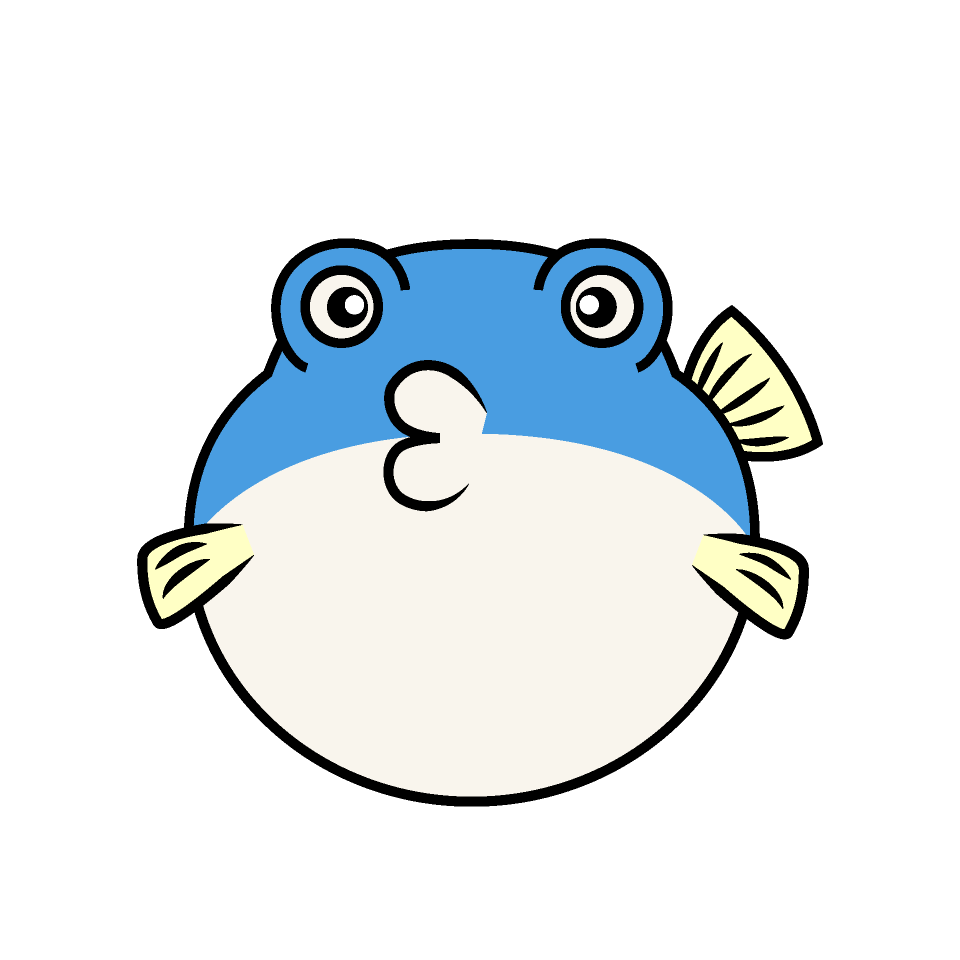
ナンボでも聞いてきいや!
忙しい時は避けるなどの配慮も必要ですが、基本的には頼ってナンボです。間違いなく可愛がってもらえます。
話したがりの性分を活かしてみる
先ほど、自分の知っている事を上手く話している時は気持ちいいと言いました。
これを経験している人は一定数いるんじゃないかなと思います。
それでは、立場を変えてみましょう。
何をされたら嬉しいのか。
自分だったらこうされたら嬉しいを参考にしてみるのも一つの手ですね。
偏見が入ってしまう

人の話を聴いている時に、「違うそうじゃない!」「それは間違っている言わなきゃ!」「こういう人だからなぁ」など個人的な感情が入ってしまう事はありませんか?
自分の勝手な先入観を入れたりすることは、「聴く事」を邪魔すると本書では言います。
その理由としては、自分やほかの人の「個性」を発見しにくくなるからとのことです。
確かに、先入観・固定観念があると、偏った見方になりますよね。
詳しくは後述しますが、本当の聞き上手の人は、「個人的な感情」は後回しにしています。
自分ではなく、「相手が」どう思ったのかを重要視するという事です。
これって結構難しいんですよね。
結局、「自分だったらどうしよう」と自分に当てはめて考えたりするからです。
近接コミュニケーション・バイアス
あなたはこの言葉を聞いたことはありますか?
バイアスとついているので、偏りの話だと思いますよね。その通りです。
ポイントは「思い込んでいる」という点です。
また、弊害というと語弊がありそうですが、ざっくり言うと話を聴いてもらえない状況の事を指します。
そして、このバイアスは一般的に「自分に思いやりがない」という理由付けで片づけてしまいがちである事が問題になります。
そうではなく、ただただ相手が自分と住んで何十年も経っているし、よくわかっているからと「決めつけている」から生まれるのです。
そうではなく、相手の事を100%知る事など不可能ですから、それを前提に「伝わっていないのか」「自分の伝え方に問題がないのか」など振り返ることが重要です。
聞き上手な人はどうしているのか?
聞き上手な人の特徴は?

そもそも聞き上手な人の特徴はどういうものがあげられるでしょうか?
- うんうんとしっかり興味を持って聞いてくれる人?
- 自分の感情に共感して聞いてくれる人?
ほとんど正解です!
細かい点は後程解説しますね。
本書での「聞き上手」な人の特徴はこう定義されています。
あなたも過去に経験ありませんか?
聞き上手な人と話していて、どんどん自分の話が出て来る。
様々な話をしていく中で、「あ、本当は私こうしたかったんや!」「話していて、気持ちが整理されたわ!」という経験です。
さらに具体的な状況でいうと、失恋した女性が女友達に愚痴を聞いてもらって、立ち直るのがめちゃくちゃ早い。
なんなら、男性の方が意外と引きずったりするという事もあると思います。
これは、個人的な見解ですが、女友達が親身に話を聴いてくれることで、自分の気持ちが整理されて、失恋を正当化することで前に向けるのではないかと思います。
話をさせていくことで、話者の気づいていない事を気づかせれる聞き手になってみたいですね。
興味をもつ
具体的な方法の話に入っていきます。
先ほどにも出てきましたが、本書でも繰り返し「相手に興味を持つこと」の重要性を説いています。
どれだけ相手に興味を持てるか。
興味を持つ手段として、「事前に相手のことを調べる」という選択肢が出てきます。
初対面の人が自分のことを調べてきてくれて、この場にいるとなると、その人と話すために調べる過程がイメージ出来て嬉しくなりますよね。
デキる営業マンは特にこの点は当たり前のようにやっている気がします。
ただただ聴く・口出ししない


先輩!こうこうこう言う理由で、こういう風にしようと思っています!そしてその後に…
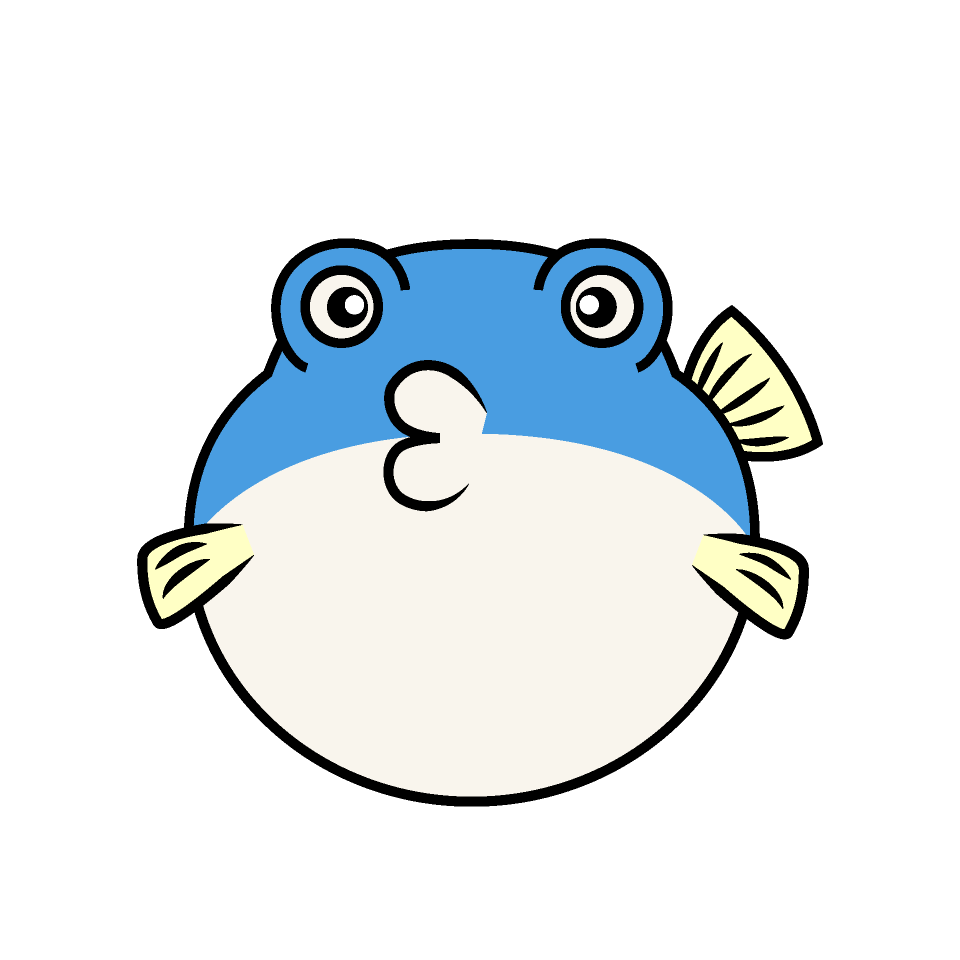
「!!ちゃうねん、そこが間違えてんねん」「やから」こうすんねんで
上記のように求められてもいないのに、アドバイスする人がいますよね。
はい、僕もその一人です…
それは本当の聞き上手ではないと本書は言っています。
話し手からすると、「そんなことはわかっとんねん」「自分の中では理解しているけど、こうしてんねん」と様々な言い分があります。
そんな不躾なアドバイスよりも、「ただただ聴いて欲しい」のです。
↓
その後に「これどう思う?」「この場合どうしたらいいと思う?」と意見を求めて来て、はじめてアドバイスをするくらいが1番いい塩梅という事です。
これ結構難しいですよね。
それくらい意識しないとみんなできないから、話を聴いてくれる「聞き上手」は何年経っても求められる人なんだと思います。
偏見を入れずにフラットに聴く
出来るだけ、話し手の感情に共感するように話しを聴くことも非常に重要だと言います。
先ほど、失恋した女性同士の会話の例を出しました。
その際に、聞き手はそれはもうどんだけやねん!ってくらいに、「わかる!!」「ヤバいよね!!」「それはつらかったね…」など、めちゃくちゃ共感して話を聴きますよね。
本書においては、共感できない聞き手なら、AIに変わってもらえればいいと言います。
確かに、ある程度の応答は出来るので、AIに代用させる事は可能ですよね。
その点に違和感を感じると思います。
という事は、少なからず「僕たちは共感してほしい」のです。
共感して話を聴いてくれる人と、話し終わった後にとても話した感じになるのは、情報量ではなく自分と同一の体験をしてくれていると思っているからです。
僕も出来る限り共感して、話を聴けるよう感情に注目してみようと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか。まとめると以下の通りです。
・誰だって「話したがり」なので、聴く事よりも知っていることを話したくなる
・なので、積極的に「教えて」貰ってみよう
・先入観は取り除いて、フラットに聴く
・本当の聞き上手は「相手が自分でもわかっていない事を引き出す人」
・興味を持って、共感しながら話を聴く
テクニックの話ではなく、根底にあるマインドの話が中心になりました。
日々の生活においても、気づかないうちにやってしまっていた事もあったかと思います。
僕も結構やらかしていました…
多くの人が気づかないうちに、やってはいけない聴き方をしているという事は、少しでも改善をすれば求められる人になり得るという事です。
なぜなら、「みんな話したがり」だから。
これを機に自分の会話を見直して、少しずつ改善していきたいと思います。
こちらの本も参考になりますので、よかったらチェックしてみてください。
そして、今回参考した書籍も貼っておきます。
それではまた!





コメント